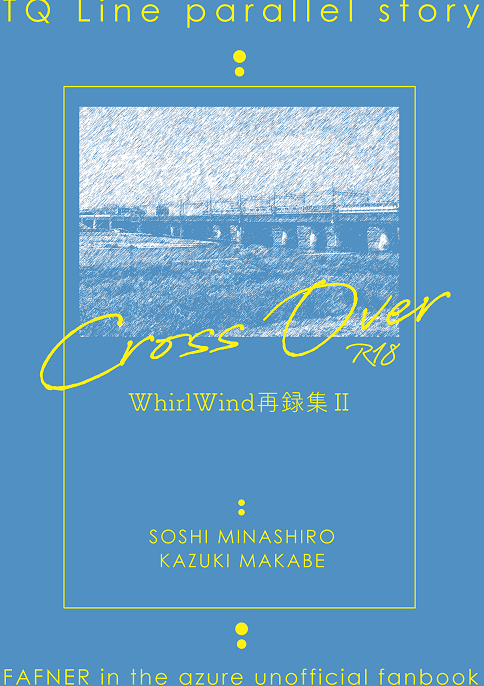
Cross Over
【サンプル】
《目次》
*…書き下ろし
1.TQ沿線編
・ここはTQ沿線、F子玉川駅徒歩五分
・牛乳を買いに行く総士の話
・コインランドリーに行く話
・一騎がコタツを出した話
・一騎の家に泥棒が入った話
・世界の果てを見たいと君が言ったから
・なんでもない日の話
・夏祭りの話 *
・うっかりデートの話
・イーハトーブへ続く道
・君とここにいる話 *
・それからの話 *
2.海外編
すこし未来の話 *
さらに未来の話 *
エピローグ
ここはTQ沿線、君の家まで走って五分 *
《書き下ろし分サンプル》
・夏祭りの話
「夏まつりだと?」
夕食時に聞かされた単語に、総士は驚いて一騎に聞き返した。
「ああ。来主から連絡があって、一緒に行かないかって」
一騎は、今晩のメインであるズッキーニと茄子のはさみ焼きを箸でつまみあげながら頷く。
このはさみ焼きは最近二人が気に入っている駅そばのデリカテッセンのもので、お互いに忙しいときや、ふと出来合のものが食べたくなったときにどちらかが店に寄って購入するのだが、これまで買ったものが好みから外れたことはない。ちなみに今日の惣菜は一騎のセレクトだ。夏期限定らしいこの惣菜はリピート確定だろう。一騎なら自分でもアレンジして作るかもしれないと思いながら、総士は夏の予定を改めて思い浮かべた。
「だが、どうせ八月には竜宮島に戻るだろう?」
はさみ焼きを一口囓りつつ、首を傾げる。
竜宮島では送り盆がある。亡くなった家族の名前を入れた灯籠を港から海に流すという風習を、総士たちの故郷は昔から守っている。その日に合わせて、島を出た人間たちも故郷に続々と戻ってくるのだ。もちろん総士たちも例外ではない。年末年始に帰省せずとも、夏だけは帰ることにしている知人も多い。送り盆は、竜宮島で生まれ育った人間にとって欠かすことのできない夏の行事なのだ。
今年も、前期試験を終えて八月に入り次第竜宮島に戻る予定で、新幹線のチケットも早々に押さえている。それまではなんだかんだとバイトやゼミの課題で追われるため、わざわざ時間を割いてまで、人出の多い東京の夏祭りに行く意味はさほどないように思える。てっきり一騎も同じ考えだろうと思ったのだが、今回に限って珍しく乗り気であるらしい。
「あんまりこっちでおまつりとか行ってないだろ」
「それはそうだが」
「来主が誘ってくれたやつ、ほおずき市があるんだ。ちょっと見てみたくて」
なるほど、と総士は頷いた。
「それはいいかもしれないな」
ほおずき市は東京の風物詩の一つだ。その開催を知らせる広告は、総士もこれまでに何度か目にしていた。
ほおずき市の由来は、港区の愛宕神社の千日詣の縁日で薬草としてほおずきを売っていたのが始まりとされ、その後、四万六千日の本元として浅草寺でもほおずき市が立つようになったと言われている。毎年七月九日と十日に浅草寺で行われるこのほおずき市が最も有名だが、それ以外でも都内のあちこちで開催される。生まれ育った地域では見たことのない風習というのもあって以前から興味はあったものの、時期的に大学の試験期間前と重なることが多く、これまで行けず仕舞いだったのだ。確かに、この機会を逃す手はないかもしれない。
心を動かされてきた総士の様子に一騎がぱっと顔を輝かせ、それならと口にした。
「浴衣着ないか? 全然着てないだろ」
「浴衣か……」
そういえばそんなものもあったと思い出す。
東京に出るときに一枚持ってきた浴衣は、進学のときに新しく仕立ててもらったものだ。だが、一騎が言うようにほとんど着る機会に恵まれていない。最初の年に、進学組のみんなで隅田川の花火大会を観に行ったときくらいだろうか。それこそあまりの人混みにが全員が疲弊し、翔子などは目を回しかけて一騎と甲洋の介護を受ける始末で、来年からはテレビで十分という話になったのだった。
多摩川でも花火大会があるが、総士の家は、あいにくとマンションの部屋の向きの都合で、音しか聞こえない。だが、一騎の部屋からは綺麗に見られる。一騎の部屋で、日が暮れても明かりをつけないまま、ベランダに続く窓を開け放して、扇風機を全開に回しながらビール缶を手に花火が打ち上がる夜空を見上げるのは、なかなかに風情があるものだった。どぉん、どぉんと音が響くたび、空に反射する光に照らされる一騎の横顔を眺めるのも。とはいえ、自宅でわざわざ浴衣を着るまでもなく、せっかくの浴衣は二年もの間押し入れにしまい込まれたままだ。
「……そうだな。こんな機会でもなければ今後もこちらで着る機会はそうないだろう」
総士が頷くと、なら決まりだな、と一騎が嬉しそうに言った。
「浴衣で行くと、店とかで割引してくれるんだってさ」
「それが目的だな?」
「かもな。あとで総士にも来主からのメールをシェアするよ。なんかいろいろ書いてあった」
「なるほど、全部来主の情報か」
操のそういうところへの目ざとさというか、勘の良さには感心する。ふはっと一騎が笑った。
「大事だろ、そういうのも。良かった。甲洋も、俺たちが行くなら行くかもって言ってたんだ」
どうやら、来主だけではなく甲洋とも話がついていたらしい。あとは総士が同意するだけだったというわけだ。
「浴衣もうちから持っていって、甲洋の家で着たらいいって」
甲洋のマンションは、祭り会場からほど近い。そこまで決まっているのなら、総士に否やはなかった。あとでほおずき市の情報を確認してスケジューリングをしておくことにする。
「楽しみだな、総士」
嬉しそうに口にすると、一騎は残りのはさみ揚げを一息に頬張った。
・君とここにいる話
一騎と身体を繋げはじめたころは、互いが一つになれるという事実に夢中になって、そのほかのことにまで意識が向かなかった。そもそも、身体を繋げるようになるまでも多少の時間が必要だった。
総士が一騎と一つになりたいと望んだのは、まだ幼いときだ。一騎と自分は、二人で一つなのだとずっと思っていた。そうでないのはおかしいことだと総士は思っていた。
だからこそ、一騎と仲違いをしたまま日本とイギリスとで別れてしまったことも、再会した先の十六歳の冬に一騎が倒れて意識不明になったことも、総士にとっては自分を見失うくらいに恐ろしく耐えがたい経験だった。一騎がいなければ、自分は正しい形を保てないような気がした。それほどに、一騎という存在を求めていた。一騎が、総士の存在証明だった。
一騎と初めて交わった日のことを、総士は覚えていない。いや、覚えているのだが、ひどく不明瞭なのだ。そんな馬鹿なと、甲洋あたりが知れば笑うだろう。でも事実だった。一騎も覚えていないという。
そのせいなのか、総士は一騎と触れ合うたびに新鮮な感動を覚える。毎回新たな発見があり、飽きることがない。
行為のことは記憶にないが、きっかけとなったやりとりは覚えている。それは一騎が長いリハビリの末に、自分で歩けるようになってしばらくたったときのことだった。
ほぼ毎日車椅子を押していた日々が懐かしくなるほど、一騎の回復は目覚ましかった。その回復力の根底にあったのが、総士を安心させたい、総士が行くところに自分も行きたいという一騎自身の強い意志だったことを総士だけは知っている。
ほら俺は大丈夫だよ、と一騎が手足を見せて笑うたびに、総士は胸が苦しくなった。一騎が回復することは喜ばしいことで、実際とても嬉しいのに、なぜか元気になった一騎がそのまま自分のそばを離れて走り去ってしまうような錯覚を抱いた。
一騎と一緒にいるためにはどうすればいいのだろうと考え続け、幼いころに抱いていた一騎とと一つになりたいという願望に帰り着いた。
一騎が欲しいと告げたとき、一騎はきょとんとした顔で総士に尋ねた。
「それ、友達じゃだめなことか?」
至ってシンプルで、かつ要点を突いた問いだった。総士は少し考えたあとに言った。
「友達でもいい。でも、友達だけでは駄目だ」
一騎は足元に視点を落とした。彼がその柔らかく独創性のある思考を一生懸命に回転させているのが総士には手に取るようにわかった。一騎はしばらくうんうんと唸っていたが、やがてぽつりと呟いた。
「俺は……総士は友達じゃないと思ってた」
「は?」
突飛する結論にさすがにぎょっとした総士の顔を見て、一騎は慌てて手を振った。
「えっと、変な意味じゃなくて。その、友だちで、幼馴染だけど、それだけじゃなくて、」
一騎は自分でも混乱しながら、それでも思ったことを訥々と口にする。
「なんだろう、もっと近いんだ。まるで俺の一部みたいな。俺の中にお前がいるみたいな。そんなことあるわけないんだけど、そうあってほしいっていうか、そうだといいなって。ごめん、何言ってんのかわかんないな。でも、お前の言う友だちだけじゃ駄目って、そういうことなのかなって、」
だんだん尻すぼみになっていく言葉をそこまで聞いた瞬間、総士は一騎を両腕で力強く抱きしめていた。
総士が幼いころから抱いていた衝動と願望に似たものを一騎が抱いていたことに、震えるほどの喜びが身体中を駆け巡っていた。一騎に縋りついていなければ叫びだしてしまいそうだった。
一騎の身体は細かったが、確かに血が通うあたたかさがそこにあった。力を込めただけ跳ね返る弾力があった。生きている人間の重たさが、両腕に収まっていた。
・少し未来の話
メールをチェックしていた真矢は、珍しい名前を見つけて目を瞬かせた。
ジョナサン・ミツヒロ・バートランド。ロンドンに住む彼女の異母弟だ。
『拝啓、マヤ。元気にしていますか』
久しぶりのミツヒロからのメールに驚きながらも最後の一文まで目を走らせ、呆気にとられる。素っ頓狂な声が真矢の口から飛び出した。
「なにそれえ?」
――俺は今、マカベとルームシェアをしています。
なぜ、こんなことになってしまったのだろうとミツヒロは思っていた。
思い続けてはや三日。二十四時間、毎分、毎秒考えている。
―本当になぜ。
なぜと思いを馳せる要因は多岐にわたる。事態は単純なようでいて、わりと微妙に混み入っていた。
皆城総士が渡英するという話は前々から真矢に聞いていた。彼の専門知識と語学力、そしてモチベーションはその選択を納得させるだけのものがあったし、ミツヒロとしてもあのまま日本に留まる人材には思えなかった。
そんな皆城と一緒に、真壁一騎も渡英すると教えられ、また彼らとロンドンで会えるのかとミツヒロは嬉しくなった。一度留学したきりの縁ではあるが、そのときに交流した彼らの人となりをミツヒロは好いていたし、日本に暮らす異母姉たちとも繋がりのある存在だ。こうして縁を持てることに素直に感謝し、二人がロンドンに来る日を楽しみにしていたのである。
だが、二人の渡英予定にいくらかの変更が生じた。
総士は、前もって一騎と住むフラットを用意しておくつもりだったらしいが、一騎の出国がVISA取得の関係で予定より一年も遅れることになったため、大学の寮暮らしを続けていた。その上、大学で組んだチームと進めていた研究が軌道に乗っていてそちらに注力せざるを得ず、結果として、一騎の渡英のタイミングに合わせて寮を出ることができなかったのである。
そんなわけで、一騎は渡英した先でもしばらくは一人暮らしをすることが決定した。一騎はそれなら自分で部屋を探せばいいやと考えたようだが、そこで強く総士が待ったとかけたのだった。
ミツヒロからすれば、総士の判断は実に正しいといえる。ロンドンの住まい探しは、初めてロンドンに暮らそうという外国人には極めてハードルが高いものなのだ。ある程度の語学力、事前調査、交渉術がなければ、悪質な部屋と契約することになりかねない。
見た目の線の細さのわりに、どんな悪環境だろうが、一騎本人はどうとでもしてしまいそうな大らかさがあるというか、妙な生存力をミツヒロは感じていたが、周囲としては心臓に悪すぎる。
研究で忙しかった総士は、一騎のフラット探しの手伝いをミツヒロに求めた。
総士本人は、どうにかして自分の納得のいく物件を自力で調査したかったようだが、彼も留学一年目の身であり、そこまでの余裕は避けなかった。歯ぎしりしそうな顔で、すまないがよろしく頼むと頭を下げられ、彼の心中を察しながらも、ミツヒロは二人の助けになるのならと二つ返事で依頼を引き受けたのであった。
フラットの条件として、一騎は寝るところさえあればどこでも、と言ったらしい。当然そんなわけにはいかないと総士は頭を抱えていた。もちろんそれを聞いたミツヒロも無言で項垂れた。無頓着というレベルを通り越している。まず、自分の身の安全を考えてほしい。
確かに欧米に比べれば、日本という国は表面上はずいぶん大らかに見えるし、カフェで自分の荷物を置いたままカウンターに注文に行く様子を見たときには目を剥いた。竜宮島などは、島民がほぼ知り合いということもあり、玄関に鍵をかけないことも普通であるらしい。
そんな環境で育ったせいなのか、一騎本人もあまり危機感が育っていないように思える。その割に勘が働くタイプらしく、これまでは本能と性格、持ち前の運動能力で危険を回避してきたものらしい。つまり、良くも悪くもいろんな意味で一番こわいタイプである。トラブルに巻き込まれてほしくない。当然ながら、最優先事項は治安のいい地区ということになった。
また、部屋タイプはベッドシットが良いだろうと決まった。部屋に専用の台所がついており、浴室のみ他の住人と共有するというタイプのものだ。日本でいうワンルームはスタジオと呼ばれるが、これは学生身分が一人ロンドンで住まうには家賃がかなり高い。ある程度のスペース共有は妥協すべき条件だった。
それから約二ヶ月、ビリーやアイにも良さそうなフラットの話を聞いたり、その都度総士や一騎に確認をとりながら、一騎の住むフラットは無事に決まった。総士の住む大学寮からも地下鉄で一駅だ。もしかしたら、これが一番頑張ったところかもしれないと、ミツヒロは自分の仕事を自分で誉めたのであった。
――それが、どうして。
という冒頭の悩みに立ち戻る。
結論を言えば、ミツヒロが総士に協力して探したフラットでの一騎の生活は、半年足らずで突然終了した。原因は、水道の故障と水漏れによる大家からの強制退去通達だった。通達から二日目には荷物ごとフラットから放り出されたのである。
・さらに未来の話
「あ、」
キッチンの棚からコーヒー豆を取り出した一騎は小さな声を上げた。
もう少し持つと思っていたストックの豆が、ずいぶんと減っていた。来週中には新しく買い足した方がいいだろう。
最近気に入って豆を買っているコーヒーショップの場所と買い物予定を頭の中で考えながら、一騎は慣れた手つきで豆を計ってコーヒーミルに放り込んだ。持ち手に手をかけてゆっくりと回せば、手動のミルは馴染んだ音を響かせ始める。同時に、挽き立ての豆の香ばしい匂いがキッチンに広がった。
横に並べたマグカップは黒と白の二つ。同じデザインの色違いだ。引越祝いとして友人たちにもらったものをずっと愛用している。もう一〇年以上は経つが、大切に使ってきてわずかの欠けもない。
時間をかけてゆっくりとコーヒーを入れ、湯気が立ち上るマグカップを両手に持つと、一騎はバックガーデンに続くコンサバトリーへと向かう。庭へ向かって大きく張り出すように作られたその場所は、日本の一般的なサンルームとは違ってそれだけで一つの空間になっており、この家ではリビングと地続きに配置されている。天井と壁はすべてガラス窓になっていて、部屋にいながらにして庭園の緑を感じられる設計だ。
スケールもデザインも異なるが、一騎にとっては縁側でひなたぼっこをしながら洗濯物を畳んだり、ときに昼寝をしていた時間を思い出すお気に入りの場所だった。
本棚や観葉植物が並ぶ空間の中心に設えた大きなソファに腰掛けて本を読む同居人の姿を見て、一騎は口元を綻ばせた。
「総士」
そっと呼びかけたが、本に集中している相方の反応はない。いつものことなので、それ以上構うことなく手にしていた黒い方のマグカップをサイドテーブルに置き、自分の白いカップを抱えてその隣に腰掛けた。
今総士と一騎が二人でが暮らす家は、ロンドンから電車で一時間ほど離れた郊外だ。もう三年前になるが、総士と親しい大学教授が老後を視野に入れた家を新しく購入し、引っ越すにあたって、それまで暮らしていたこの家に住む気はないかと総士に持ちかけたのだ。
総士と一騎はロンドン市内のフラットから郊外に移動することをちょうど検討していたときで、二人揃って教授夫婦の家に下見がてら訪問をし、その場で引っ越しを即決した。
イギリス人は家を育てる、といわれる。新築よりも中古物件が歴史ある建物として尊重され、新しく入居した人は自分の生活スタイルや好みに合わせて家をリフォームする。そのリフォームも、ほとんどが業者に頼むのではなく、自分たちの手で少しずつ変えていくのだ。
家は、住人を映し出す鏡だ。住みながら心地よく育て上げた家は、また次の住人へと受け継がれる。その歴史が家の価値を高め、さらに町の景観を作り上げている。
この文化を知ったとき、こんな形の継承もあるんだなと一騎は驚いたものだった。イギリスの住宅の平均築年数は七十七年となっており、日本の倍以上だ。そんな家の一つを、総士と一騎もまた新しく受け継いだ。
自分たちも内装を好きにリフォームしていいのだと分かってはいるが、受け継いだこの家の居心地の良さに、あまり手を加える気にはなれずにいる。寝室と総士の書斎は壁の色を変えて家具の配置も変えたがその程度だ。キッチンも現代的なものにすでにリフォームされており、広さも設備も充実していて、フラットでの小さなキッチンに慣れていた一騎からすれば天国のような場所だ。このほか、庭は少しずつ二人の好きな花に植え替えていて、一部では野菜も育てている。
ここはロンドン市内よりはるかに家賃が安く、部屋の面積も広い。市内に暮らす便利さも確かにあったが、一騎は今の暮らしの方が断然気に入っていた。もちろん総士もだ。
中心部から少し離れたところで暮らす気ままさは、二子玉川に暮らしていたあのころを思い出すものがある。大学進学時から卒業後までを過ごしたあの六年間は、今も一騎の中で鮮やかに息づいている。懐かしい故郷の島の風景と一緒に。
・ここはTQ沿線、君の家まで走って5分
かくりと頭が落ちかけて、はっと総士は目を覚ました。
――朝の五時半か……。
霞む視界の中で壁時計を確認して、がしがしと一つに結わえた長髪をかき回す。
レポートを仕上げたまま、ソファで気を失っていたらしい。提出レポートが三つも重なってしまったために、予定外の修羅場を見てしまった。なんとか日付が変わる前にすべてを送信し、別の授業の調べ物を続けていたのだが、途中から記憶がなくなっている。部屋の明かりはついたまま、カーテンの向こうがすでに明るくなりはじめている。
総士は首をぐるりと回して肩をもみほぐすと、腰掛けていたソファから立ち上がった。
立った瞬間に凝り固まっていた身体が悲鳴を上げ、思わず呻く。これは最近の運動不足も祟っているかもしれないなと反省しながらつけっぱなしだった部屋の電気を消し、ベランダの方へ近づいて閉めきっていたカーテンと窓を開けた。
入り込んでくる朝方のひんやりとした空気が心地よい。靄のかかった思考が晴れていく。空に雲は無く、今日は予報通りに晴れるようだった。
今日は午後まで授業がない。このままベッドに行って寝てしまうべきだとは思ったが、そのまま歩いて洗面台へと向かう。顔を洗って倦怠感と眠気を飛ばすためだ。ついでにシャワーを浴びようとしたが、軽く浴槽を洗って風呂を沸かすことを決めた。もっとも自分が浸かるためだけではない。
それは、これからここにやってくる幼馴染のためだった。
総士が暮らすこのマンションから川を一つ隔てた先にあるアパートでは、総士の幼馴染がすでに目を覚ましているはずだ。
いつも早起きの彼がすることは一つ。歯を磨いて顔を洗い、ランニングウェアに着替えてアパートを飛び出すと、多摩川の土手を駆け下りて朝日に照らし出される河川敷を走りに行く。
そして、日課のランニングを終えた幼馴染は、まっすぐにこちらに向かってくるのだ。
総士に会うために。それを総士はよく知っている。
幼馴染――一騎の顔を思い浮かべて、総士はかすかに目を細めて微笑んだ。
TQ沿線シリーズ再録集。書き下ろし5本を含みます。二人のこれからとはじまり。